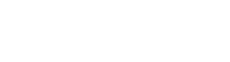北木島へ行くには、一日に片手ほどの回数しかないフェリーだけがアクセス手段。
山から切り出される石が知られているとはいえ、観光地ではないし、海が美しいと言ってももっと便利なところに海水浴場はいろいろあるし、いったい何をしに行ったの、と聞かれるのだが、心を洗いに行ったのよ、なんて答えたらキザになるだろうか。
実際、本土の笠岡へ帰る便も少なくて、うっかりしていると最終便も夕方まだ明るい間に出てしまう。船着場が閉められた後は、港には人影もなくひっそりし、潮騒の音以外、何も訪れるもののなくなった海辺の寂しいことといったら。
だが、この島の絶景は、最終フェリーが出た後にこそある。
とろりと凪いだ水面、船影ひとつない海上。そこを金色に染めて落ちていく夕日と、入れ替わるように天上に現れる星々の輝き。だがそれも一瞬の心ときめく時間に過ぎず、空がとっぷりぬばたまの闇に沈んだあとは、海陸の定めもない宇宙がそこに残る。
こんな素朴な海辺の家で、島の人々は何年、何百年と、何を思って暮らしてきただろう。
そんなことに想いを馳せれば、実際の目で見る以上のこころの絶景が、ふと見えてきたりする。
たとえば、この島に伝わる「流し雛」の風習。ここの島では三百年という昔から、麦わらや厚紙などで小さな帆立船を作り、紙雛を乗せ、波打ち際から流すのである。もちろん、雛といえば旧暦3月3日の満潮時。このエッセーが掲載になるのは夏で、まったくの季節違いと思われるのだが、実は、紙雛は毎月一体作って、十二体そろえるのだ。だから、毎月がひな祭り、とでも言えようか。日々、子供が病気にならないように見守り、月々、健康であることを祈り続ける。そして、年々、無事の成長を感謝する。また一体、また一体と、紙雛の数に願いを託しながら。
雛の島。それが北木島の、こころの風景といえるだろう。
こうして作ったひな人形を乗せた船は、波打ち際から波に乗り、沖に出たなら海流に運ばれ、はるか紀州沖まで旅していって、女性の守り神と言われる加太の淡島神社へたどりつくのだという。
いやいや実際に調べてみれば海流はその方向には行かないらしいし、第一、今では環境保護で、流した雛は沖合でゴミにならないよう集められてしまう。
だがそんなミもフタもない話はともかく、かつて一生をこの島で過ごし、外の世界を知らない女性達が、我が子には幸あれと願って雛を流した風習は、けなげでありながらどこか切実だ。彼女たちが海の向こうに夢見た幸せは、どんな形をしていたのだろうか。
そんな、島独特の伝統や、昔話を聞くことができるのも、外海から閉ざされた島の夜のひとときならでは。
とれとれの魚にほろ酔いの一献を傾ければ、せきたてられる時計などない島の時間が、波の音と一緒に、長い歴史に揺られた果ての風景を見せてくれる。

作家。兵庫県在住。1989年、神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)でデビュー。著書多数の中、『お家さん』(新潮社)で第25回織田作之助賞。文筆のかたわら、テレビコメンテーター、ラジオパーソナリティなどでも活躍。