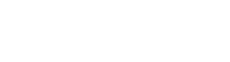「民芸」と「民藝」。その違いを初めて知ったのは、若い日にドライブがてら倉敷を訪ねた時だった。
同じ発音だが、民芸というと、おみやげ物屋に並ぶようなその地特有の田舎風の小物一般がそれ。一方、ことさら旧漢字を使う民藝の方は、大正時代、柳宗悦や河井寛次郎、浜田庄司らが唱えた主義主張に沿った品々を言う。すなわち、置いて眺めるためのアーティストの銘の入ったような作品ではなく、日々の暮らしで庶民が使う丈夫な道具ばかり。無名の職人が作ったものでありながら姿も自然に美しく、「用の美」とも言われている。
倉敷にある「倉敷民藝館」もこの旧字だ。
江戸時代の蔵を活かした展示館に入るなり別世界に来た気がしたのは、それだけ私たち現代人が日本の伝統品から遠ざかってしまったからだろう。三つある展示室の常設品は、そのほとんどが初代館長外村吉之介さんが世界各国を巡って集めたものだそうだ。見ているだけで、民藝とは何か、わかったような気になったことを思い出す。
久しぶりにここへ足を運ぶことになったのは、あの日見た江戸時代の手仕事の品がふと思い起こされたからだった。長編小説「帆神 北前船を馳せた男」を執筆する中で、岡山にも北前船が寄港していたと知ったが、いったい何を積み込んでいったのだろう。手掛かりはここにあるような気がした。
北前船とは、大坂の浪華津を出て、瀬戸内の港、港でさまざまな物資を積み込み、下関で日本海(北前)に出て、越前越後、奥羽、そしてはるか蝦夷地へ航海していく物流の船だ。帰りは蝦夷地の特産品の昆布や鰊などを積み込むが、行きの積荷は実に雑多。徳島の藍、大洲の和紙、内子の蝋燭、竹原の塩……。瀬戸内沿いには多彩な特産品があった。各藩がこぞって商品作物の栽培を奨励し、地場産業が栄えるよう力を注いだからである。
そして岡山からも、北前船がどっさり運んでいけば寒い北国で喜ばれ、儲けられる人気商品があった。――そう、畳表や花筵(はなむしろ)である。
当時の蝦夷地は寒冷なため米がとれず、刈り取った後に残る藁もない。したがって縄一本、筵一枚、温暖な瀬戸内で作られたものを船で運んで行かねばならなかった。
買い手があれば、作り手も励みになる。高く売るには品質が大事で、手が込んでいて美しければ高価になり、生産意欲も高まっただろう。もともと手先の器用な日本人。手間暇かけつつ、無駄なく見た目も美しい、地方色豊かな品が生み出されていく。
柳宗悦は日本を「手仕事の国である」と言った。民藝館に展示された花筵は、どれも驚くばかりに精緻な作り。眺めていると、きっとそれらがはるかな北国で、冷たい座敷を暖かく彩り重宝されたことがうかがえる。そしてその華やかな面積の上で長い冬を過ごしつつ、またその地その地の手仕事がはぐくまれていったことが確信できるのだ。
作家。兵庫県在住。1989年、神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)でデビュー。著書多数の中、『お家さん』(新潮社)で第25回織田作之助賞。文筆のかたわら、テレビコメンテーター、ラジオパーソナリティなどでも活躍。