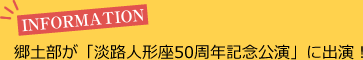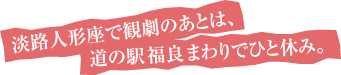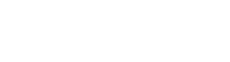ドライブ途中に立ち寄った淡路SAで、思いがけず人形浄瑠璃を見た。
テレビや写真では知っていたが、実物を見たのは初めてだった。
淡路島の高校生が仮設の舞台で一生懸命に人形を操っていて、大勢の観客が
次第に、人形の軽妙な動きに引き込まれていく様子が印象的だった。

淡路SAでは年に数回、南あわじ市の中学生、
高校生による人形浄瑠璃の公演が行われている。
(平成26年9月13日、淡路三原高校)
淡路SAでの印象が強烈だったので、一度人形浄瑠璃をじっくり見てみたいと淡路島の南端、南あわじ市の福良港にやって来た。福良港は古くから四国の鳴門と淡路島を結ぶ連絡船が出入りした港で、現在は渦潮見物の観潮船が発着している。この港の正面に、人形浄瑠璃を常時上演しているという「淡路人形座」があった。
劇場1階は、180席ほどのこじんまりとした造りで、舞台と客席が近く、いかにも芝居小屋といった趣だ。開演まで、演目のあらすじが書かれたチラシを読む。妖怪狐が出てくるらしい。面白そうだ。期待して待っていると、黒衣姿の演者が人形を抱えて現れた。上演前に、人形の仕組みや操り方などを解説してくれる。ひとつの人形を3人の演者が操るのだという。実際に、かしら(頭)と手足の動きを合わせて見せてくれたが、その自然な動きに驚く。普段見る機会がないので、そんな初歩的なことも知らなかった。
 淡路人形座は、淡路人形浄瑠璃を受け継ぐ唯一の「座」 淡路人形座は、この劇場を本拠に一年を通して人形浄瑠璃を上演し、全国各地に出張公演も行っている。海外でも、これまでに20ヵ国1地域に招かれて公演した実績を誇る。座員は最高齢の人間国宝、鶴澤友路師(101歳)から19歳の新人まで現在16名。すべて、地元出身者である。 |
 開演前の解説 座員が実際の人形を手に、その仕組みや遣い方、かしら(頭)と手足の動きを分担する3人の役割などを分かりやすく解説する。人形はこの劇場が保有しているだけで190体ほどもあり、すべてが長い年月使われてきたもの。100年を超すものも現役で使用されている。 |
 三味線 太棹の三味線が低音の重厚な響きで、劇の流れを盛り上げていく。 |
 太夫 物語の内容や登場人物の言葉を、情感たっぷりに語って聞かせる。 |
 人形づかい かしらと右手を遣うのが主遣い、左手を担当するのが左遣い、足を担当するのが足遣いである。この3者の動きが合わないと動きが不自然になってしまう。「足8年、左手8年、かしら一生」と言われ、厳しい修行が求められる。 |
幕が開いて驚いたのは、舞台の華やかなこと。人形の着物はすばらしく色鮮やかで、背景の書割りの色や絵柄の派手さにも目を見張った。舞台上手から、太棹三味線の低音が響き、浄瑠璃の語りが始まった。
物語が進むにつれて、人形は感情の起伏を表すように眉や目が激しく動き、左右の手先も顔の向きに従って実に自然に動く。舞台が近いので、細かな仕草もよく見える。あまりにも自然な所作に見とれていると、人形を操っているはずの黒衣の存在を忘れてしまいそうだ。三味線と浄瑠璃の掛け合いもテンポ良く、まるでミュージカルを見ているような迫力。何百年にもわたって庶民の心をとらえてきた芸能のもつ、強烈なエネルギーをずしんと感じた。
 玉藻前曦袂「神泉苑の段」 たまものまえあさひのたもと・しんぜんえんのだん お姫様に化けた妖怪狐が、陰陽師に退治されてしまうというお話。早替わりや宙吊りなど、観客を驚かせる趣向(ケレン味)が盛り込まれた淡路人形浄瑠璃ならではの演目。 |
 人形浄瑠璃は三位一体の総合芸術 写真左から鶴澤友吉さん(三味線)、竹本友庄さん(太夫)、吉田千紅さん(人形づかい)。三味線と語りの掛け合いが難しい。「どちらがリードするかは、演目やその場の状況で違ってくるので上演前には毎回、間合いを確かめるようにリハーサルを欠かさない」と言う。20年を超すキャリアを持つお2人の言葉に芸の厳しさ、奥深さを感じる。人形づかいの吉田千紅さんは、入座2年目。この三者の連携がぴたりと合った時に、人形に魂が吹き込まれる。 |
|
淡路人形浄瑠璃とは 淡路人形浄瑠璃の源流は、兵庫県西宮のえびす神に奉納されていた「人形操り」の神事である。西宮から淡路に百太夫という人形づかいが移り住み、技芸を伝えた。人形操りはその後、浄瑠璃語りや三味線の伴奏と結びつき、江戸時代に至って人形浄瑠璃の原型ができ上がる。大阪では常設の劇場で上演され歌舞伎と並ぶ人気を博したが、いっぽう淡路では40以上もの人形座(プロの芸能集団)ができ、それぞれが遠く東北から九州まで巡業して歩いた。現在、日本各地に伝承されている三人遣いの人形浄瑠璃の多くは淡路が起源とされる。ユネスコ無形文化遺産に登録されている「文楽」の名称は、幕末に淡路から大阪に進出した植村文楽軒の旗揚げした一座の名前「文楽座」に由来する。 |
 |

淡路人形座
【DATA】
住所/兵庫県南あわじ市福良甲1528-1地先
Tel/0799(52)0260
定休日/毎週水曜日。
公演/1日5回(10時・11時・13時・14時・15時に開演)
料金/大人1,500円、中高生1,300円、小学生1,000円、幼児300円
伝統芸能を次の世代に継承するために、淡路人形座の座員が
公演の合間をぬって地元の小中学校や高校などで指導している。
人形座の吉田新九朗さんが、淡路三原高校郷土部へ
稽古をつけに行くというので同行をお願いし、
学校の許可を得て練習風景を見学させてもらった。

淡路三原高校はのどかな田園風景の中にあった。下校中の生徒達が笑顔で会釈をしてくれる。校門を入ると、体育館からクラブ活動に励む生徒達の元気な声が聞こえてきた。こんな青春真っ盛りの雰囲気の中で、人形浄瑠璃のような古い芸能に取り組んでいる生徒達がいるのか。彼らはどんなふうに練習しているんだろう。舞台裏をのぞかせてもらえる期待感で、わくわくしながら郷土部の部室へ向かった。三味線の音や浄瑠璃を語る声が聞こえてきた。東京での公演に備えて「戎舞」の特訓中だという。大きな鯛を釣り上げるえびす様の動きを見た新九朗さんから、所作の一つひとつに厳しい声が飛ぶ。プロの稽古場さながらで、生徒達よりも見ているこちらが緊張してしまった。

休憩時間に人形浄瑠璃を始めた動機を聞いてみた。「小さい頃に人形座の出張公演を見て興味をもったから」と言う。南あわじ市では、人形浄瑠璃はイベントなどで演じられることが多く、子ども達のごく身近にあるのだとか。やりがいはと聞くと、「お年寄りが感激して涙を流してくれた」「初めて人形浄瑠璃を見た人が、面白いと言ってくれた」「ここが見所だと熱を込めて演じた箇所で拍手が沸いた時は、やった!と嬉しくて」と、楽しそうに答えてくれる。まだ高校生なのに、お客さんの反応をきちんと観察しながら演じているのだ。すごいな。彼らがひたむきに稽古に励む姿を見て、こんなふうに500年の伝統が受け継がれ、そして未来に引き継がれていくのだなと思った。先ほどの人形座での感動がよみがえってくる。人形座の来月公演も楽しみになってきたぞ!


「淡路人形浄瑠璃魅力発信事業・西宮公演」
開催日/2015年1月6日(火)
会場/兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホール(兵庫県西宮市高松町2-22)
開演/13:00、入場料/S3,000円、A2,000円、B1,000円(全席指定・税込)
予約・問合せ先/芸術文化センターチケットオフィス
Tel/0798(68)0255(10:00~17:00、月曜休み)
インターネット予約:http://www.gcenter-hyogo.jp

兵庫県立淡路三原高校郷土部
60年前から淡路人形浄瑠璃に取り組んでいて、その実力は折り紙つき。過去には、海外公演も4回経験している。学校内外のイベントに参加して上演する機会が多く、日々の練習は欠かせない。現在の部員数は14名。三味線も浄瑠璃語りも人形づかいも、すべて生徒だけでこなすという高いレベルを維持している。

観潮船乗り場の隣に、旅の疲れを癒す足湯「うずのゆ」がある。渦潮のようにお湯がまわる「うず潮足浴」、「タコ壺型の足浴」、「手浴」など種類もいろいろ。福良港と鳴門海峡を眺めながら、しばしの休憩に最適だ。温泉の効能は、神経痛・筋肉痛・関節痛・疲労回復など。
足湯・うずの湯
【DATA】
住所/兵庫県南あわじ市福良甲1528番地7地先
入湯/無料
利用時間/10:00~17:00。年末年始(12/30~1/3)は利用時間が短縮。
お問合せは、南あわじ観光案内所(Tel:0799-52-2336)まで。
福良マルシェには産直野菜・水産加工品・特産品の売り場があり、併設のイートイン・スペースでは名物の淡路島ピザや新鮮な刺身も食べられる。

焼きたてのピザ(500円)に自分でフライドオニオンを敷き詰め、さらに玉ねぎスライスを好きなだけトッピングして、淡路島特製の玉ねぎドレッシングをかければ完成。淡路島の玉ねぎの甘さが際立つ、ユニークな新名物だ。ほかにも、オニオンフライ(150円)、淡路島コロッケ(150円)のほか、ふぐの唐揚げなども。

福良漁協が鳴門海峡で養殖している、3年物のとらふぐは天然ものに負けない美味しさ。「淡路島の天然ふぐと3年とらふぐの味くらべ丼」(1,290円)は、2月下旬までの季節限定メニュー!

福良マルシェ
【DATA】
住所/兵庫県南あわじ市福良港
Tel/0799(52)1244
営業時間/10:00~18:00、定休日/無休