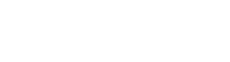海辺の生まれじゃないのに、ぽかぽか暖かい春の日には、ふらり、港に出かけてみたくなる。穏やかで、まったりとした凪の上を、いくつもの船が行き交う海に面した港の町。風が柔らかに吹く小高い場所があって、花も咲いて、そして一人よりは、居心地のいい誰かと一緒ならば、なおいいなあ。
などと考えるだけでも港に出掛ける気分は盛り上がる。むろん、そういう相手がいなくても、一人でいても寂しくなく、時間を忘れて過ごせるような、どこかなつかしく思える港町なら、瀬戸内ぞいにはいくつもある。
たとえば尾道港。すぐ背後には海抜百四十メートルの大宝山があり、中腹の千光寺からは、港町はもちろん、遠く対岸の愛媛へと続く島々も一望できる。寄り添うような家々の屋根瓦、それらを割って港に通じていく道と船舶の活気。山の続きには天寧寺の三重塔も甍を連ね、傍らには山上へ上るロープウエイの動きが町の生命感を伝えてきて――。
シンプルな自然を眺めるのとは違い、ここでは海と調和しながら暮らしてきた人々こそが風景の主役だ。遠い昔、この地にこんなありがたい寺々を興した先人がいて、それを慕った純心な人々がとぎれなく、遠く広く船で参拝に訪れたという歴史を知れば、人間っていとおしいなと思わずにいられない。
今ここにはどんな人がいて、どんな人生を送っているのだろう。そんなことを思って私も港を眺めているが、つい口ずさんでいたのは若い日にヒットして耳に馴染んだ歌謡曲。昨年('20)亡くなった昭和の大作曲家、筒美京平の作になる『早春の港』という歌で、なんとも港にぴったりすぎる。
歌は、海辺の町でめぐりあった恋人たちが、春の陽ざしの中、港を歩く姿を描いている。特に恋に浮かれたりせず、ただ二人で港を見ているだけのひととき。彼の方はちょっと暗い影があって、どうしてこの港町にやって来たのか、過去のことは語りたがらない。彼ってまるで「あてなくさすらう小舟みたい」と彼女は思う。でもどうでもいい。二人が出会えたこの港町で今を生きる、そのこと以外は重要じゃない。彼女の願いはただ一つ。ふるさとを持たない彼に、ここの海辺の青さを教えるように、やさしさを教え、愛で包んで、「心の港になりたいの」って思うだけ。
この歌、南沙織が歌っていたといえば覚えている方もいるだろう。その港町で、二人はいつまでも幸せに暮らしたか、それとも悲しく別れたか。また想像が広がっていく。
港には、出船入り船、ささやかな人間の出会いと別れがどれほど詰まっていることか。それは決して永遠ではないはずなのに、ここの港をふるさととしてとどまって、町を愛して暮らす人々の存在は今も不変だ。
春になると港に心惹かれる理由は、きっとそこに、変わることなく人が暮らして、いつでも待ってくれているから。そんな心の港へ、また出かけて行こう、花咲くうちに。
作家。兵庫県在住。1989年、神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)でデビュー。著書多数の中、『お家さん』(新潮社)で第25回織田作之助賞。文筆のかたわら、テレビコメンテーター、ラジオパーソナリティなどでも活躍。