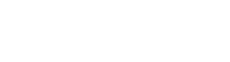高知県西部、四万十川に近い土佐佐賀漁港は、江戸時代からカツオ漁が盛んだった。伝統的な土佐の一本釣りの漁法は400年以上受け継がれていて、今もこの港を母港とする一本釣り漁の船団はフィリピン沖から九州、東北、北海道近海までカツオを追って操業している。一度、母港を出ると半年以上は戻らず、行く先々の港に獲れたてのカツオを水揚げしながら移動していくのだという。
 |
日戻りカツオを求めて、港に建つ「カツオふれあいセンター黒潮一番館」を訪れた。ここには、元漁師のおじさんや漁師の奥さんたちがいて、カツオのタタキづくり体験をさせてくれる。ここで、日戻りカツオの正体を教えてもらった。小型船で高知県沖の漁場に朝早く出て、その日のうちに港に戻り水揚げしたのが日戻りカツオだという。さすが、カツオの本場、話を聞いているうちに頭の中は新鮮なカツオを頬張る妄想でいっぱいだ。早く食べたいと喉が鳴る。
 カツオの一本釣り イワシを撒き餌にして魚群を引き寄せ、疑似餌を付けた竿で一本釣りする |
 カツオの水揚げ・出荷 船から揚げたカツオは、その場ですぐに1本ずつケースに入れられ、トラックで高知市や県外へ直送される |
カツオふれあいセンター黒潮一番館では、60㎝ほどの大きなカツオの頭を落とすところから、元漁師のおじさんが包丁に手を添えて、さばき方を教えてくれる。焼く時は、ドラム缶に藁束をドッと放り込んで炎を上げ、焼き加減を調整してくれた。その間、カツオの習性から新鮮なカツオの見分け方、タタキの語源まで楽しい話を聞かせてくれる。タタキとは、皿に並べた身の上に天日塩や醤油を握った手の甲で身を軽くたたきながら味を馴染ませることからきたと教わった。藁で焼くのは、土佐独特のやり方。自分で焼いてみて分かったが、魚が新鮮なので、強い火勢で短時間焼くだけで良く、藁焼きの火力がちょうどいいのだ。
自分でつくったタタキを食堂で食べる。タタキの薬味はネギだけ、新鮮なのでポン酢も使わない。塩だけでいけるが、好みで、醤油と味醂を煮詰めたタレを少量つけて食べてもいい。柔らかいけど弾力がある身と、塩が引き出した濃厚な旨味が口の中で広がった。「これがカツオなんだ!」と一人うなずいた。
 ①大きなカツオを一本丸ごと、左右の胸ビレのところに包丁を入れて頭を落とす |
 ②背ビレは包丁を打ち付けるようにして、引きはがす ②背ビレは包丁を打ち付けるようにして、引きはがす |
 ④大きいフォークのような道具にのせて火の上に。藁が燃え上がると一瞬で身の色が変わる ④大きいフォークのような道具にのせて火の上に。藁が燃え上がると一瞬で身の色が変わる |
 ③腹と背から包丁を入れて三枚におろす |
 ⑤たらいの水でさっと熱をとってから、1㎝程度の厚みに切る |
|
 ⑥皿に盛ったら天日塩を振って、手でなじませる ⑥皿に盛ったら天日塩を振って、手でなじませる |
||
| カツオふれあいセンター黒潮一番館 【DATA】住所/高知県幡多郡黒潮町佐賀字海雲寺374-9、Tel/0880-55-3680、営業時間/11:00~15:00、定休/火曜日(祝日営業) |
||
| カツオのタタキづくり体験 【DATA】実施期間/3月中旬~11月(3日前までに要予約)、受入人数/3名~200名(詳しくは電話にて問合せを)、体験料金(税込)/4名までは1人4,000円、5名以上は1人3,200円、所要時間/約2時間(食事の時間を含む) |
||