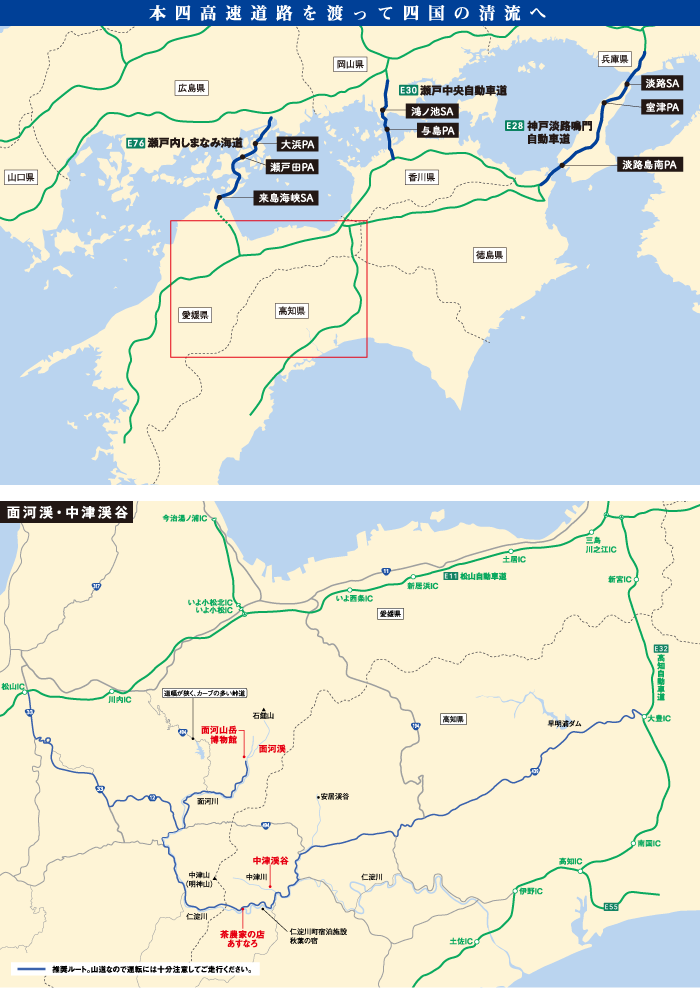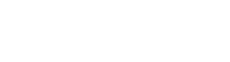ホーム > 瀬戸マーレ vol.49 > エメラルドグリーンの清流で大自然の営みを体感
情報誌「瀬戸マーレ」

面河山岳博物館から続く遊歩道から、幻想的なまでに美しいエメラルドグリーンの水が見える。
面河渓 愛媛県久万高原町
エメラルドグリーンの清流で
大自然の営みを体感
石鎚山の南麓に広がる面河渓(おもごけい)。
仁淀川の源流域にあり、エメラルドグリーンの水をたたえた面河川や、
奇岩奇勝が連なり、動植物が命を輝かせている。
仁淀川の源流域にあり、エメラルドグリーンの水をたたえた面河川や、
奇岩奇勝が連なり、動植物が命を輝かせている。
悠久の時が刻んだ
自然のアートに魅せられて
あまりに水が透き通っていて深さがわからないぐらい川底がくっきり見える。透明な水は場所によってエメラルドグリーンに輝き、仁淀ブルーとは違う美しさだ。
面河渓ははるか昔の地球の営みを体感できる場所。変化する岩の景観に痕跡をたどれ、水の美しさにも関係しているから見逃せない。
散策は面河山岳博物館から始めよう。このあたりは三波川帯(さんばがわたい)と呼ばれる約1億年前にできた緑色の変成岩(へんせいがん)が土台になっている。だから川床に緑の岩が多く、エメラルドグリーンが際立って見えるのだ。
ところが5分ほど歩いて錦木(にしきぎ)の滝に来ると雰囲気が変わり、岩が黒くなる。約1500万年前に現在の石鎚山周辺で火山活動が起こり、三波川帯の上に火砕流(かさいりゅう)が堆積した。滝から上流は火山灰が固まった黒い凝灰岩(ぎょうかいがん)なのだ。板状の割れ目や、水や石で浸食された深い谷が山水画の世界をほうふつさせる。

- 錦木の滝を境目に地質が変わる。向かって右側が三波川帯の変成岩、左側が火山活動でできた凝灰岩。
さらに上流に行くと、白い岩が多くなった。マグマが地下深くでゆっくり固まった花崗岩(かこうがん)が地表に露出しているのだ。花崗岩の一枚岩が高さ約100m、横幅200mにわたってそびえる亀腹(かめばら)は、スケール感に圧倒される。河原に下りて、白く滑らかな岩肌をさらさら流れる水に足をつけてみた。驚くほど冷たい。ここは川が生まれ出る石鎚山のすぐ麓なのだ。この大自然をもっと感じたくなった。

- 水の流れによって花崗岩が磨き上げられ、川床は板のように滑らか。

- 一年を通して湿潤、冷涼な気候で、ヒメレンゲなど渓谷沿いに生育する植物が多数見られる。

- 面河渓でも特に幅の狭い峡谷、関門。高温の火山灰が固まるときに生まれる節理と呼ばれる横の割れ目が美しい。秋は鮮やかな紅葉が彩りを添える。

- 亀のお腹のようにつるっとした花崗岩がほぼ垂直にそそり立つ亀腹。黒く見えるのは風化によるもので、本来は真っ白!
面河渓谷プライベートガイドツアー

「自然だけでなく、歴史、文化などの話も交えて面河渓の魅力をご案内します」と松本勝さん。
DATA
住所/愛媛県上浮穴郡久万高原町若山 TEL/0897-47-6030 ※要予約
(株式会社ソラヤマいしづち)
所用時間/約4時間(昼食は各自持参)
料金/15,000円(9名様まで一律料金)
[実施人数]1~9名
[開催時期]4~11月
[申込締切]実施日の7日前
緑色に輝く神秘的なコケの森へ
面河渓はコケの宝庫。地面や岩、倒木、遊歩道の欄干にまで緑のじゅうたんを広げている。 樹木にぶら下がるように生えるコケを見られるのも、空気中の湿度が高い深い谷ならでは。 500種類以上が生息すると考えられ、詳細は面河山岳博物館で調査中だが、近づいて観察するとさまざまな色、形、手触りを楽しめる。

コケがつくり出す
ミクロな世界をのぞこう

- 透明感のある繊細な葉がこんもり。小さな森のよう。

- オオカサゴケを囲むようにいろんなコケが群生。

- 花のように愛らしいコケが集まり、お花畑みたい。

- 繁殖のために伸びた胞子体が潜望鏡のようで面白い。

- 濡れた芝生のよう。よく見ると先がカールしている。

- 細かい枝分かれが針葉樹を思わせ、触るとふかふか。
好奇心を呼び起こす「山」の
博物館
面河渓散策は、遊歩道の入り口にある面河山岳博物館に立ち寄ってからスタートするのがおすすめ。石鎚山や面河渓の誕生の過程や、豊富な生物が紹介されている。

模型や標本で面河渓を深く知る
どこからか鳥のさえずりやカエルの鳴き声が聞こえてくる。愛らしい草花やチョウにも出会える。面河渓を歩いていると、どんな動物や昆虫がいるのか、どんな草花が四季を彩るのかを知りたくなる。
それを教えてくれるのが面河山岳博物館だ。約3000点もの資料が展示され、石鎚山系や面河渓の誕生の歴史を岩石を見ながら学べ、昆虫の標本や植物模型などから種類や特徴を知ることができる。
感動するのはジオラマ。ムササビ、テン、クマタカ、ヤマドリをはじめ、希少なニホンモモンガやニホンカモシカなどのはく製が、森にいるかのような姿で展示され、こんなに生き物がいるのかと驚かされる。夜行性でめったに会えない天然記念物のニホンヤマネもいるという。
ここで知識を手に入れ、実際に散策しながら見て、姿を想像することで自然の豊かさをより実感できる。知りたい意欲もどんどん高まって季節を変えて訪れたくなった。

- ニホンモモンガの生息に必要な樹洞(木の穴や隙間)が面河渓にはある。

- 翼幅が広く精悍なクマタカ。エサを確保できる生態系があればこそ。

- 四国最大面積のブナ林が広がり、いろいろなクワガタがいる。

- 標高の高い山で見られるマイヅルソウ(模型)。葉がハート形で初夏に白い花、秋に赤い実をつける。
面河山岳博物館
面河渓の自然だけでなく、石鎚山の山岳信仰や登山についても紹介。祭礼「お山開き」の様子が石鎚山のパノラマ模型で描かれ、石鎚山系の壮大なスケールの中に面河渓があることもわかる。

DATA
住所/愛媛県上浮穴郡久万高原町若山650ー1 TEL/0892-58-2130
営業時間/9:30~17:00(入館は16:30まで)
休日/月曜日、祝日の翌日(月曜が祝日の場合は開館し、火曜休館)、12~3月の土日祝、年末年始、展示替期間中
料金/一般300円、小中学生150円 駐車場/あり