11月6日(火)に倉敷芸文館で「第19回全国学習フェスティバルまなびピア岡山2007」の総合閉会式があり、エンディングを盛り上げるため、岡山初となる「ゆるキャラ祭りinまなびピア岡山」が開催され、「わたる」も参加しました。このゆるキャラ祭りでは、岡山県内21種類のゆるキャラが集合し、それぞれの自己紹介やコント、体操など披露!!普段は見られないキャラクター同士のパフォーマンスは、必見でした。また、ゆるキャラ全員とお客様との「ももっち体操」も実施し、大いに盛り上がりました。さぁ、みなさんも「ももっち体操」をしましょう!!

このイベントは、「世界一住みたいまちおかやま」を合言葉に、世代参加・家族参加・社会参加 をキーワードに、地域のワクワクする機会や必要なことに触れる機会を創出しようと、S:Sports P:Public O:Okayama を テーマに活動する若手社会人と大学生(岡山大学、ノートルダム清心女子大等)を中心とした地域づくりサークル「SPOxT」により企画実施していただきました。。。

ゆるキャラにより岡山県内の新たな連携が出来きました!!
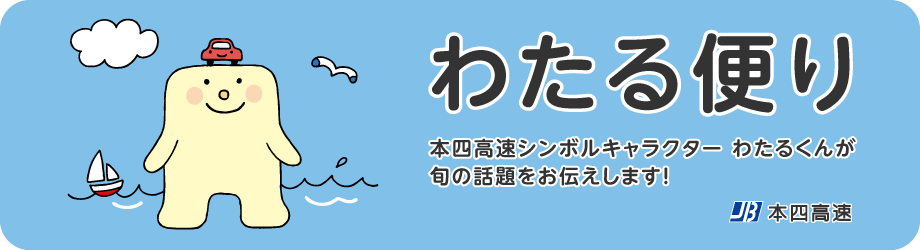

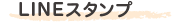

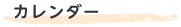
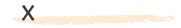

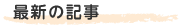
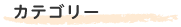

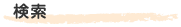




 行楽シーズン真っ最中!!実りの秋、紅葉の秋です。車好き・旅行好きなあなたに贈る割引情報のご案内です。。。
行楽シーズン真っ最中!!実りの秋、紅葉の秋です。車好き・旅行好きなあなたに贈る割引情報のご案内です。。。










