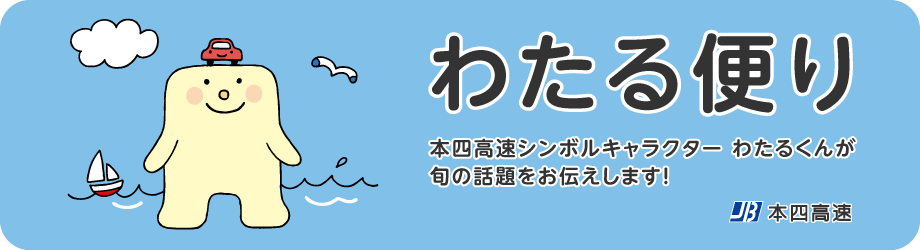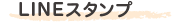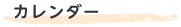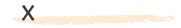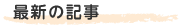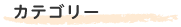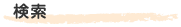今年全通10周年を迎えるしまなみ海道。自然・景観・文化・環境等の観点 から大変高い評価を受けています!!東京圏で行われるPRイベントでは、注目度抜群の「日本初の海をわたるサイクリングロード」の視点から『しまなみ海道』の魅力を発信していきます。
 ★愛媛県観光プロモーション★
★愛媛県観光プロモーション★
1月14日(水)~16日(金)
羽田空港第二ターミナル2Fにて開催。
日本最大級の羽田空港のスペースを利用した
観光振興プロモーション。
イベントタイムでは、坊ちゃん&マドンナ&わたるのコラボPRを行います!!
~イベントタイムスケジュール~
1/14(水)13:00&15:00 1/15(木)11:00&13:00&15:00
1/16(金)11:00&13:00
また、ふるさと情報プラザでは、1/5~1/31「しまなみ縦走2009グッズ」
を展示中です。テーマは、「2009なごみ旅 北国から南国まで」

展示物HP→http://homepage3.nifty.com/fjp/tematenzi.htm