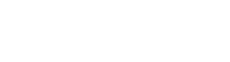実は私はサカナがあまり好きでなかった。海から遠い山の町で生まれ育ったせいだろう、子供の頃に、美味しい海鮮を食べた記憶がないのである。
ところが瀬戸内に面した兵庫県の高砂市に嫁いだならば状況は一転する。
まず、ご近所さんが、朝から釣りに行ってきたからと、カンパチやカレイ、アサリなど、季節ごとに獲物をお裾分けしてくれるのなんて日常茶飯事。また、浜手に住む漁師さんが、その日獲れた魚を入れた木箱を自転車に積んで町内を回ってくるのも珍しくない。むろん魚屋さんは何軒もあり、焼き穴子の香ばしい匂いが通りに充満しているといった様子。たとえるならば、海辺に近いあの町は、海からの恵みを受けて暮らす〝海幸彦〟の町だった。
当然、各家々にも、台所には出刃包丁に刺身包丁、よく手入れされた道具が揃っていて、どんなサカナも手際よくさばいていくのが海幸彦の主婦たる者。義母も例に漏れず、毎日といっていいくらいサカナ料理をした。
時折、見ているだけの私に義母は言う。
「こっちのサカナは私が刺身におろすから、そっちのサカナはあんたが捌いてくれる?」
しかしこちとら、サカナといえば調理済みのパック入りしか見たことがない。びちびち跳ねる青いサカナを絞めるの開くの、そんなの無理。目が合うだけでぎゃーっと包丁を捨てて義母の後ろに逃げるのがオチなのだ。
この家からは、夏になれば遊びに行くのは瀬戸内の島と決まっている。夫が子供の頃は、家から海水パンツで浜辺へ出掛けたほどに海が近く、高度経済成長期に浜が埋めたてられてしまって以降も、向いの海から呼ばれるように感じるのだろう。
海岸に行くと、家島諸島がよく見えた。夕日の島影、雨後の島影。日に日に眺める島々は、どんな天気の日にも欠くことの出来ない風景の座標軸だ。
その中の男鹿島へはわずかに船で30分。
浜辺に一軒ある民宿では、漁師でもあるご主人が朝の漁で獲ってきた魚が生け簀に泳がせてあり、お客はそれぞれ、スズキがいい、シャコが食べたいと、生け簀から選んで注文する。料理するのは奥さんの役。そりゃもう手慣れたもので、生きたタコなど注文すれば、バケツでぐにゃぐにゃ暴れて脱走しようとする上から塩をぶっかけ、刃物も使わず料理が始まる。敵も必死だ、素揉みする奥さんの腕にぴちゅぴちゅ吸い付き抵抗するが、非情な料理のプロはものともせずにタコ全体をくるり裏返し、ダイナミックにも生きながら墨や内臓をとりだす手際よさ。むろん、できあがったタコ刺しときたら絶品で、口に入れればなお舌にぴちゅぴちゅ吸い付くほど。
味付けの秘訣を訊いたことがあるが、水は一滴も入れず塩と醤油だけ、という回答には苦笑した。素材が新鮮ということは、それだけで天然の恵みなのであろう。
あの町の暮らしがなければ、私は一生サカナを食わず嫌いで終わっていただろう。海からやや離れた町に住んでいる今、見よう見まねで海幸彦の料理に挑戦している私なのだ。

作家。兵庫県在住。1989年、神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)でデビュー。著書多数の中、『お家さん』(新潮社)で第25回織田作之助賞。文筆のかたわら、テレビコメンテーター、ラジオパーソナリティなどでも活躍。