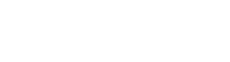我が家の床の間には、家を新築した時のお祝いに夫の友人たちが贈ってくれた備前焼の大壺がある。場をとるだけに、どうしてこんなに大きいの? そのくせどうしてこんなに口が小さいの? いったい何に使うの? と、そこを掃除するたび壺に尋ねている。
それというのも、私にとっては備前焼といえばもっと、使えるヤツのはずなのだ。
子供の頃、祖母の部屋でみつけた謎の箱。中には、何に使ったものやら黒く汚れたまましまいこまれた備前焼の器が入っていた。
「それはなあ、鉄漿に使う道具や」
祖母によれば、かつて女性のたしなみだったお歯黒の液を入れて使った日用品という。
「頑丈で、落としても割れへん器やったから、いまだにこんなとこにあったんやな」
ふうん、とおとなしく聞いた後、私は悪戯心で器を落としてみた。本当に悪い子供だった。すると器は地面に落ちて数個に割れた。
「割れへん、って言ったから……」
べそをかきながら言い訳したのを記憶するが、叱られたかどうか覚えていない。
もう使わないからと、許されたのかもしれない。ともかくそれが、私の最初の備前焼だった。
次に備前焼を見たのも子供の頃。割れないどころか、初めから割れていて、断片を継ぎ接ぎされた壺だった。
私が生まれたのは播州三木城の城下町で、遊び場は城跡だった。後に作家になってから、『虹、つどうべし 別所一族ご無念御留』という作品に書くことになるが、戦国時代、その城には播磨の総帥別所氏がいて、羽柴秀吉の中国攻めに先立ち、三木合戦が起きたのだ。
城跡からは割れた備前焼の瓶がまとまって出土した。炭化した麦粒が付着しており、食糧貯蔵用だったらしい。「三木の干し殺し」として二年ちかい籠城戦が行われたため、中の米はすべて食べ尽くされたのであろう。
いわばその瓶は城内の人々の命をつなぐ糧の瓶、戦い続ける意志を量るバロメーターだ。備前焼であるのは、毛利氏から三木城へ兵糧が送られた史実を裏付けるかもしれない。
だがそんな歴史を何一つ語らず、割れた瓶は継ぎ合わされて、静かに整列している。
祖母のお歯黒鉢も戦国の瓶も、どちらも人が日常、触れて使った実用の品だ。落として割れないはずはないが、それだけ丈夫であること、使い勝手のよさを信頼されたのだろう。
それにひきかえ我が家の壺は、花を活けるにも醤油や油を入れるにも適さず、不意の備えにも使えそうにない。空のまま、でん、とそこに居座るばかりが能なのである。
とはいえ眺めれば胴のふくらみの面積は大きく、そこに流れる緋襷という赤い焼きの模様もどこか温かい。今や同居人のようなその壺に、今日も尋ねる。――いったいあなたは何のための壺? と。
たしかに何の実用にもならないが、そうやって手を止め、目を留め、目的を考えこませる、それがこの壺の役目なのかもしれない。平和の世とは、まさに壺が割れずに存在し続ける時代をさすのだから。
むろん、壺は是とも非とも言わないが。

作家。兵庫県在住。1989年、神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)でデビュー。著書多数の中、『お家さん』(新潮社)で第25回織田作之助賞。文筆のかたわら、テレビコメンテーター、ラジオパーソナリティなどでも活躍。