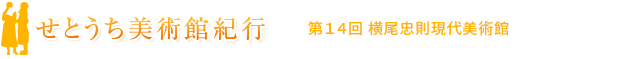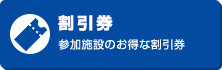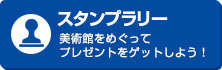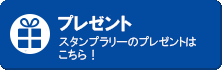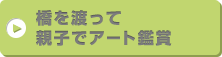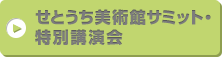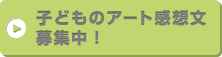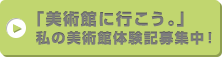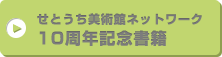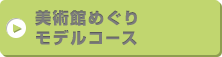HOME > せとうち美術館紀行 > 第14回 横尾忠則現代美術館

横尾忠則現代美術館に関しての対談4
大学との提携や、高校生の観覧無料化を実施

田中:
大学と協定を結び、そこの学生は学生証をもって来館すると曜日に関係なく割引料金にすることもやっています。最近は関西学院大学や神戸松蔭女子学院大学と協定を結びました。横尾忠則現代美術館だけでなく兵庫県立美術館と一緒にやっています。
山木:
それは貴重ですね。
館長:
今年から高校生もすべて無料にしました。兵庫県だけでなく他県の高校生も学生証を見せれば無料です。
山木:
それは全国的に見ても画期的ですね。土日だけ無料という所はありますが、平日も含めてというのはないですね。

山本:
大学との連携という点では、兵庫県立美術館の学芸員のOBが教えているということもあるのですが、開館以来、神戸芸術工科大学のインターンシップを受け入れ、毎年夏にアーカイブ資料の整理などをお手伝いいただいています。
山木:
学芸員資格取得の要件に実習が必要ですが、それと関わりがあるのですか。
山本:
それとは別です。ただ単位にはなるようです。
あと武蔵野美術大学と甲南大学から博物館実習生を受け入れています。当館は非常に特殊な美術館で、講義室もなく、美術にまつわるいろんなことをオールラウンドにレクチャーするのは難しいのですが、資料整理などに特化したかたちで実施しています。
山木:
アーカイブをまとめるというのはリアリティがありますね。
山本:
それに特化した形で先方の大学にご了解いただいています。武蔵野美術大学はアーカイブにもすごく力を入れておられるので、横尾さんの資料整理に関しても一部ご協力をいただいています。横尾さんの記事が出ている書籍をデジタル化するためいったん武蔵野美術大学に運んで、書誌情報の入力とスキャンをしてもらっています。
山木:
横尾さんを扱った情報をファイリングして整理しているということですか。
山本:
そうです。書誌情報の入力とデジタル化の部分をやっていただき、データを共有するという形です。まだそれは継続中です。
ユニークなワークショップで子どもたちの興味を高める

山木:
子どもたちへの教育普及ということでは中学生もその中にはいると思いますが、どういう形でアプローチされているのですか。
山本:
トライアルウィークという職業体験を受け入れています。後は展覧会ごとに必ずワークショップをやるようにしています。
山木:
中学生向けのワークショップですか。
山本:
ケースバイケースですね。中学生に特化していることは少なくて、大人の方もけっこういらっしゃいます。
山木:
小中学生限定にすると親が入れなくなりますから、幅を広げておいた方がいいですね。
田中:
展覧会ごとのワークショップは季節によって親子で来られているケースもあります。夏休みは宿題をされているのかもしれません。子ども向けのワークショップは定期的に開催しています。
山木:
具体的にワークショップの内容を教えていただけますか。

山本:
「横尾忠則の冥土旅行」(2018年2月24日~5月6日)という展覧会の時は、横尾さんの最新作が20点ぐらい並びました。
その作品は女性のポートレイトシリーズで、顔の前にトイレットペーパーや靴、オブジェなどを重ねて描いてあって目の表情が読み取れず、ミステリアスな印象を与えます。自分たちもこの女性になりきってみようということで、「○○の女~ヨコオ流・仮面変身術」というワークショップを開催しました。
まず担当学芸員がレクチャーをし、そこから自分なりのオブジェをつくります。実際はマスクをつくるのですが、マスクの上にどんなオブジェを乗せるかというのをそれぞれ自由に発想してもらい、紙粘土とかオブジェとかいろんなものを利用してつくります。そして写真を撮り、実際のマスクは持って帰ってもらい、写真はホール1階のエントランスに展示をしてお客様にも見てもらうようにしました。
山木:
それは女性限定ですか。
山本:
いえ、性別も年齢も問いませんでした。小さい子が一人で3つぐらいつくったり、大阪芸術大学の男子学生が一生懸命つくっていたり、一緒にやっているのが面白かったですね。出来上がりの展示がきれいに仕上がり、「横尾さんの作品ですか」と言われるぐらいでした。
山木:
他にもありますか。

山本:
「決戦! ビリヤード絵画」というワークショップも開催しました。絵の具をつけた球でビリヤードをするというもので、チームに分かれて対戦します。するとビリヤード台が汚れるわけです。それを結果として展示する、ゲームがそのまま造形につながるワークショップです。
田中:
球が転がった跡がそのまま絵になるので抽象画みたいです。
山木:
それも面白そうですね。
田中:
子どもさんが楽しんでやっていました。
山木:
そういうワークショップは、プロセスや企画、あるいは出来上がった段階で、横尾さんに情報は伝えられているのですか。
山本:
「横尾忠則現代美術館ニュース the Y+Times」でお知らせしていますが、おそらくほとんど読んでおられないと思います(笑)。
山木:
横尾忠則さんのつくり方や考え方を理解してもらうために一助となるという広い考えで実施されているのですか。

山本:
「ビリヤード絵画」を行ったときの展覧会は「わたしのポップと戦争」(2016年4月16日~7月18日)という、横尾さんのポップな部分あるいは戦争体験みたいなものをモチーフにした作品を展示しました。
横尾さんの初期のグラフィック作品は非常に鮮やかなものがあるんですけれど、よく見ると赤と青と黒い線、そして紙の白と3色しか使っていません。そこを子どもたちに見てもらって、「たった3色でこんなにかっこいい絵を描けるんだね、みんなも負けずにできるかな」みたいな感じです。
山木:
企画は学芸員さん同士で考えられるのですか。
山本:
教育普及担当の嘱託学芸員が展覧会のテーマを踏まえてまず案を出します。それを展覧会の担当学芸員とキャッチボールしながら形をつくっていく感じになります。
山木:
「ビリヤード絵画」は、合同研修会「先生のためのミュージアム活用術」と共同開催とありますが、合同研修会というのは何ですか。
山本:
学校の先生方と美術館の学芸員との交流プログラムみたいなものです。美術館と学校の連携を考える会でワークショップなどを実施します。大きな美術館の場合は先生のためだけの機会として行うのですが、当館の場合はなかなかマンパワーが大変なので一緒にやっています。定員10名が一般参加、もう10名が学校の先生方という形ですね。「ビリヤード絵画」の時はたぶん一緒にやったんだと思います。
山木:
「観光ペナントをつくろう」というワークショップについても教えていただけますか。

山本:
このときは「ヨコオ・ワールド・ツアー」(2017年4月15日~8月20日)という展覧会をやっていました。横尾さんが世界中を旅した足跡とその作品が世界中にあるわけですね。その観光ガイドをつくりたかったんです。この展覧会の図録を持って行けば世界中で横尾さんがここでこんなことしたということがわかる、ファンにとってはすごく楽しい観光ガイドで、こういう地球の歩き方をするのというものです。
それを踏まえてワークショップでは、架空の観光地のペナントをつくろうとしたわけです。横尾さんには、あり得ないものを組み合わせて不思議な絵をつくるというコラージュの考え方があります。
山木:
思い出の場所と横尾さんの作品の旅した場所を組み合わせると説明が書いてありますね。
山本:
そうです。それで予想外の謎の場所のペナントができるという趣向でした。ただペナント自体を最近あまり見ないので、どうやって説明しようかと担当者はずいぶん頭を悩ませていました。
山木:
それを教えてあげるのも教育ですよね。海外旅行をしてなくても、想像力を働かせて自分が行ったところとつなぎ合わせればいいわけですから、楽しいワークショップですよね。
山本:
そうなんです。
山木:
子どもたちへの教育普及が魅力的なワークショップという形で行われていることがわかりました。その他にも、小学校、中学校、高校が子どもたちを美術館に連れてくるということがあると思うんですね。年間どのぐらいありますか。
山本:
学校から引率しての来館は、たとえば2015年度でしたら生徒数が合計で362名、引率者数が26名です。
山木:
内訳は中学校、高校、大学が多いですね。小学校はないんですか。
山本:
小学校は学校の外へ連れ出すのがなかなかハードルが高いようです。
山木:
出前授業みたいなのはしないのですか。
山本:
あります。レギュラーにはやっていませんけれど。老人ホームに行ったことがあります。