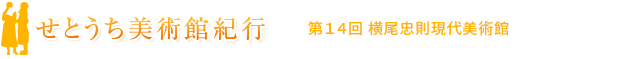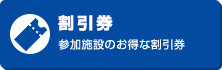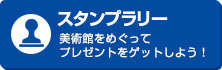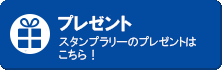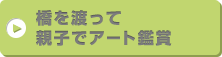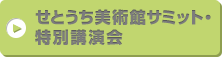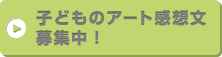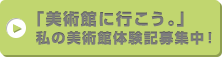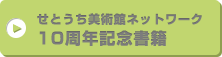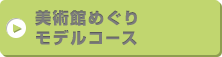国際的に活躍する美術家・横尾忠則。出身地の兵庫県にある横尾忠則現代美術館は、横尾氏本人から寄贈・寄託された作品と膨大な資料を収蔵し、その魅力にあますところなく触れることができる場所です。作品からほとばしるエネルギーは圧倒的で、アーカイブルームにある資料から創作の秘密に迫ることができます。

施設外観

展覧会ごとに展示方法を工夫。「画家の肖像」(2018年5月26日~8月26日)では、ブルーの壁面にグラフィックデザイナー時代の作品、白の壁面に画家宣言以降の作品が展示されている。

ロック・カルチャーに精通し、国内をはじめ、サンタナなど海外アーティストのアルバム・ジャケットも数多く手がける。写真は、『オペラ横尾忠則をうたう』(ジ・エンドレコード)
横尾忠則現代美術館に関しての対談1
■出席者
鳴門教育大学大学院教授 山木朝彦さん(以下山木)
横尾忠則現代美術館館長 蓑 豊さん(以下館長)
兵庫県立美術館王子分館長 田中 敬一さん(以下田中)
横尾忠則現代美術館学芸課長 山本 淳夫さん(以下山本)



■対談日
2018年6月29日(金)
兵庫県立美術館の分館として2012年に誕生

山木:
蓑(みの)館長は横尾忠則現代美術館の館長ですが、兵庫県立美術館の館長もなさっています。この2つの美術館はどういう関係にあるのですか。
館長:
この場所は、もともと兵庫県立近代美術館が生まれた場所なんです。
阪神・淡路大震災が起こり、文化で何とかして心を癒せないかということで、HAT神戸という海岸沿いの地域に近代美術館の機能を移し、震災からの復興のシンボルとして兵庫県立美術館が新たに生まれました。
同時に、ここ旧・近代美術館の建物と場所をどうしようかということになり、もともと公募展をやっていたこともあり、兵庫県立美術館の分館という位置づけで、一般の絵画や書道など様々な芸術文化を発表するギャラリーとして再スタートさせました。

横尾忠則現代美術館は、国際的にも名声があり、兵庫県のシンボル的な作家である横尾忠則さんを象徴する美術館をつくろうというコンセプトで、分館の一部を改築し、個人名を冠した美術館として2012年にオープンしました。
山木:
なるほど分館なんですね。
田中:
スペース的には西館の部分が横尾忠則現代美術館で、残りの部分は「原田の森ギャラリー」という愛称で、一般の方に使っていただけるギャラリーにしています。
都道府県立のギャラリーとしては西日本で最大規模のギャラリーで、年間20万人くらいの入場者数があります。それだけ関西にとって大事な拠点になっています。
館長:
この場所自体がかつて「原田の森」と呼ばれていたんですね。

山木:
それで蓑館長が両方を兼任されているということなんですね。距離的にも兵庫県立美術館と横尾忠則現代美術館は近いですから情報交換や学芸員の交流など結構なさっているんですか。
館長:
もちろんです。
田中:
学芸員も基本的には両館を兼務しています。
膨大な数の作品を制作、公開制作も多い
館長:
横尾忠則現代美術館にたくさんの人が来てほしいと思っています。ですから来館者の多い兵庫県立美術館の特別展の有料チケットの半券を横尾忠則現代美術館に持ってくればディスカウントするようにしています。
山木:
具体的にはどれぐらいディスカウントするんですか。
田中:
2割引になるようにしています。
山木:
それはセールスポイントですね。

田中:
横尾さんの絵というとどうしても好き嫌いがあったりするんですけれども、結構食わず嫌いの人がいるんじゃないかと思うんですね。そこで兵庫県立美術館に来る人に一度横尾忠則現代美術館に来てもらいたい、裾野を広げたいという思いがあります。
山木:
好き嫌いがあるかもしれないということですが、横尾さんの画集やエッセイ集、小説は小さな図書館にまで津々浦々入っていて、利用者には人気があって貸し出し中も多いです。ポピュラリティという意味では抜群で、岡本太郎や池田満寿夫が亡くなった後、同時代美術の作家としてはトップですよね。
館長:
そうですね。いまだにすごい数の作品を制作していますから。描きだすとすごく早いんです。当館でも展覧会の時に公開制作をしますが、一日で描いてしまうこともあります。一時は必ず展覧会ごとに公開制作をしていました。
山木:
横尾さんは躊躇なく公開制作をされて、度胸がありますよね。

館長:
なかなか普通の人はやらないですよ。自分のテクニックを見せたくないですし。
山本:
画家宣言した当初はアトリエをお持ちじゃなかったんですね。だから場所がなくて、いろんな美術館に行って描かせてくれ、公開でいいからと、そうせざるを得なかったんです。お客様さんが見ている中で描くと、一人で描いているときとは違うエネルギーをもらって違う絵ができるのが面白いらしいです。見ていても飽きないですよ、どんどん変わっていきますから。